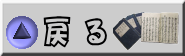文永元年1444年、水原秀家がその祖、政家が下條平三郎に譲った越後舟原の地とはどこなのか、昔で言えば下條の耕地で諏訪町から山口町東西で、 北西は羽越線両側から現在の水原自動車学校を越えた所までのようだ。そして下條平三郎は、下條と山口の中央にある山王林に館を築き、関東管領で 越後守護の山内上杉家の代官として支配した。
守護神として山王権現を祀る。山口氏神として山王宮、日吉神社となったのである。
文承二年(一二六五年)の下條孫次郎から慶長三年(一五九八年)の下條薩摩守実親まで三三三年間、下條氏は続いた。 歴史に名が残っている、下條孫次郎、平三郎家久、駿河守貞尚、薩摩守実頼の4名で、采女と言われていた。
●下條駿府守貞尚(下條忠親の父である) 明応八年(一四九九年)長尾為景(越後守護代)の家臣・下條駿府守貞尚が駒林小字に要害館を築き、地域を開拓しました。
その館跡は、養廣寺の手前の地で、現在は公園という名目で、残っています。
その後、貞尚は大永六年(一五二六年)疫没したと思われます。 菩提として一寺を建立し華蓮寺と称し、曹洞宗に改め、出湯の華報寺の末寺で現在の養廣寺です。 約二五年間、駒林に館を築き治めていた模様です。
その後、上杉景勝の家臣、直江兼続は、帰依し下條駿府守の追善を祈るため 中国の宗時代の通元が書いた「紺紙金泥般若波羅密教1巻」と祝木一斤(香木)、方金千斤(多額の金銭)を養廣寺へ寄付しています。
※(養廣寺)と要害舘は1532年の同年に建てられました。
下条駿河守の父が建立したと伝えられています。
この揚北衆の戦国時代は、住職は100年不在です。下条駿河守に追善で、お寺には直江兼続から送られた、紺紙金泥般若心経・香木・方金千疋などが献上されています。この要害舘は、今はお寺の向かいにもありますが公園となっています。 ここで過去に発掘した際に2.17cmの鉄砲の玉が出土しました。この眼の前の駒林川から、物資を運んだ形跡があり養廣寺裏の道路は今も、水原火葬場の前を通っています。 この道を真っ直ぐに行くと笹岡城跡に続きます。