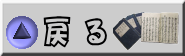応仁二年(1468)。開山様は月窓明潭大和尚です。
月窓様は須賀川の長禄寺(観音寺本寺)を開創の後、 晩年に越後長尾氏の招請によ り、観音寺を開かれました。境内には樹齢5百年を超えよう程の銀杏、欅、 杉が聳え立っていますが、開山様お手植えの樹木とも伝えられています。
開山様より九代器堂存朴大和尚のころまでは法脈が正しく伝えられていたようでしたが、
その後、 祝融などに見舞われ山内は疲弊した時代となりました。越後の 武将上杉謙信は手厚い信仰を寄せ、 深く外護し復興の一助をなしたといわれます。
謙信没後は当山中興の開基として墓所を設け、位牌を献じて供養に務めてきて います。
戊辰戦争が当山に甚大な被害を与えました。
慶応四年(1867)七月二十七日頃、 逃亡中の会津藩兵士多数が当山に来襲し、しばし身を寄せていたのですが、 八月二日早朝遂に官軍との激しい交戦の場となり、 建物、樹木の一部などが無残にも灰と化してしまいました。
幸いに事前に煩海筏舟大和尚の弟子三十五世寶海 玉舟大和尚の 指揮により会津藩兵士の力を借り、過去帖、什物、書画などは、裏山に持ち出し難を逃れました。
また、謙信没後、景勝は更に観音寺に帰依して寺領安堵を進め、地元はもとより水原福田方面にまで寺領は広まって行きました。
景勝は寺内に[心字池]を中心とした柏樹園という名園を築いていますが、これが林号の命名ともいわれています。
家紋は上杉です。上杉謙信の第二墓所です、ここは上杉謙信の分骨されています。
上杉景勝の心字池があり、竜虎の石があり雨乞いに使われたそうです。
また、戒名で[不識院殿心光謙信大居士]は、ここだけであり、一般に[不識院殿真光謙信 法印大阿闍梨]です。
裏山宝珠山の八千刈を上杉謙信の所領とした石碑があります。
安田長秀等の地区でもあり息子の有重は上杉景勝の従兄弟という間柄です。 住職の母様より、聞きましたが旧暦毎年8月中旬(稲刈り後なので現在の9月中旬)に上杉のお祀りを観音寺で行なっていたそうです。