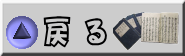文治年間(一一八五~八九年)柏崎琵琶島の領主宇佐美氏が守護の命により下越阿賀北を取締るため、宇佐美左衛門亮高治を派遣した。
高治は館を構え、同地一帯を支配したと言われている。その後、高治は源義経に関わる奥州の乱で藤原泰衛の残党鎮圧に出陣した 琵琶島領主が苦戦したため援軍にて奥州に向かったものと思われる。
室町時代に入ってから応永の大乱で親関東公方派の守護・長尾邦景を討つため上杉房朝方について兵を挙げた上杉房資が 応永二〇年(一四二三年)に白河氏の守る堀越城を急襲した。
室町後期の蒲原郡段銭帳に堀越孫六の農地一一〇町歩と出ています。
明応年間(一四九二年)その後、代々堀越氏の居城であった。
文禄四年(一五九五年)検地契機として直江兼続は菅名城(村松)在番 の丸田俊次に対し、武田信清の所領であった堀越分のうち指出検地を契機として地頭に返却し開発を続けるように命ずる。
堀越分を直轄地として代官に俊次を任命している。
慶長三年(一五九八年)村上藩領となり、正保国絵図に二七〇石余とある。
寛文一三年(一六七三年)組々数、高付大庄屋付では堀越組、大庄屋二平新兵衛に属し、
貞享元年(一六八四年)郷村高辻帳には高九八八石八斗余とある。
宝永七年(一七一〇年)幕府領となる。